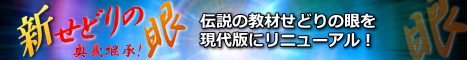-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
中央アフリカ単独介入に協力“二の足” 仏、EUで孤立感
3000万チャレンジプロジェクト
【ベルリン=宮下日出男】中央アフリカの人道危機を受け、今月初めに軍事介入に踏み切ったフランスに孤立感が漂っている。欧州連合(EU)の各国は介入を支持する一方で、単独行動に対する踏み込んだ協力には二の足を踏んでいるからだ。こうした事態は安全保障分野でのEU協調の難しさも示している。
オランド仏大統領は20日、EU首脳会議終了後の記者会見で、「軍事行動への参加を求めているのではない。見たいのは欧州の存在感だ」と、介入に向け欧州諸国への協力を求めた。
首脳会議は、「内戦や大虐殺の回避に寄与した」(ファンロンパイEU大統領)と仏軍介入を支持。来年1月に外相らがEUの関与策を検討することにした。だが、仏紙フィガロは「オランド氏の目標は達成できなかった」と報じた。
仏軍は部隊1600人を展開し、新旧政権派武装集団の武装解除を急ぐ。だが、イスラム過激派武装勢力を相手としたマリへの介入と違い、中央アフリカは敵味方の判別が困難で、「より厄介」(専門家)ともされる。介入直後には仏軍兵士2人が殺害され、仏国民の介入への支持は51%から44%に下落した。
フランスは作戦をEU全体の活動とすることで負担軽減を模索。だが、期待したポーランドなどの部隊派遣は見送られ、加盟国は輸送支援などにとどまる。首脳会議では戦費を賄う共通の基金の創設も狙ったが、加盟国の反対で頓挫した。
EUでは外交・安全保障政策の決定には全会一致が必要だが、介入は仏単独の行動。加盟国としては意思決定に関与できない活動の支援はしづらい。アフリカへの影響力を保ちたいのでは-などと、フランス側の思惑を推し量る向きもある。【関連記事】PR -
“ダブルエース”不在のバルサをペドロが救う、ハット含む5ゴール演出
3000万チャレンジプロジェクト
[12.22 リーガ・エスパニョーラ第17節 ヘタフェ2-5バルセロナ]
リーガ・エスパニョーラは22日、第17節を行い、首位バルセロナは敵地でヘタフェと対戦し、5-2で逆転勝ちした。前半14分までに2点を失ったが、FWペドロ・ロドリゲスのハットトリックなどで5点を奪い、大逆転。2連勝で勝ち点3を積み上げ、アトレティコ・マドリーと同勝ち点で首位を守っている。
前半10分に先制を許したバルセロナは同14分にもCKから失点。負傷離脱中のFWリオネル・メッシに加え、FWネイマールも出場停止で欠く中、立ち上がり早々に2点のビハインドを負ったが、“ダブルエース”不在のチームをペドロが救った。
まずは前半34分、MFセスク・ファブレガスのスルーパスに抜け出したペドロがループ気味に右足でミドルシュート。GKの手を弾いてゴールネットを揺らすと、同41分にはMFアンドレス・イニエスタのスルーパスを再びペドロが受け、左サイドから中に切れ込み、右足で同点ゴールを奪った。
前半43分には左サイドを抜け出したDFジョルディ・アルバがマイナスに折り返し、DFに当たったこぼれ球をペドロが左足で流し込む。わずか10分間でハットトリックを達成し、3-2と逆転に成功した。
後半立ち上がりもヘタフェにチャンスをつくられたバルセロナだが、ここをしのぐと、後半23分、ペドロの右クロスをセスクが頭で叩き込み、4-2。同27分にはペドロが獲得したPKをセスクが沈め、5-2と試合を決定づけた。今季2度目のハットトリックを達成したペドロはこれで早くも今季通算10得点。メッシ、FWアレクシス・サンチェスの8ゴールを抜き、チーム内得点王となった。【関連記事】 -
草津で「キッズダンスフェス」全国25チームがダンスバトル-「Cats'n Rats」が初の連覇 /滋
3000万チャレンジプロジェクト
イオンモール草津(草津市新浜町)で12月22日「第5回キッズダンスフェスティバル2013 スーパーグランプリX'mas決戦大会」が開催され、彦根市の姉妹チーム「Cats'n Rats(キャッツンラッツ)」がグランプリを獲得、大会初の連覇を果たした。(びわ湖大津経済新聞)
【画像】 準グランプリに輝いた「Boogie Down Bounce」
小学6年までのダンスを楽しむ子どもたちに発表の場を提供することを目的に開催されている同大会は今年で5年目。本年度行われた3回の予選大会(全84チーム参加)で入賞した24チームに昨年度グランプリの「Cats'n Rats」を加えた計25チームがスーパーグランプリ(賞金20万円)をかけてダンスバトルを繰り広げた。審査にはERI(姫、CaLeidScope)、YURI(甘い飴)、KAZUKIYO(BOUNSTEP)、Chikaya(AIR:LIVE+PENGUIN)のプロ審査員4人と一般審査員8人があたった。
グランプリに輝いた「Cats'n Rats」は、彦根市の三松新菜さん(小学6年)と彩葉さん(小学4年)の姉妹ダンスチーム。選曲、振り付け、衣装を全て2人で考案。昨年も絶賛されたキレのいいヒップホップダンスを披露、見事25チームの頂点を射止めた。「どのチームも上手でレベルが高い中、優勝できてとてもうれしい。私たちらしさを出せて楽しく踊れた」と姉の新菜さんは笑顔で喜ぶ。「去年もとてもうれしかったが2年連続で優勝できて本当にうれしい。これからも頑張りたい」を妹の彩葉さん。準グランプリには「Boogie Down Bounce」(兵庫県)(2年連続)が輝き、審査員特別賞には予選大会ステージ3優勝の「ずぅ。」(大阪府)が選ばれた。
審査委員長のERIさんは「構成力、振り付け、衣装、パフォーマンスなど年々参加チームのレベルが上がり、大人が負けてしまうんじゃないかと思うくらい。指導する先生方の頑張りも感じられる。上位入賞チームは振り付けを『踊らされている』のではなく自分が感じたままに素直に踊っていた。それが自然な笑顔、楽しさ感につながり見るものに伝わる。審査もナチュラルにいいなと思うチームを評価した」と語る。
同フェスを主催するNPO法人キッズダンスフェスティバル理事長石澤正義さんは「大会を主催して5年。計18ステージを見てきたが数段レベルが上がってきている。まさに『じぇじぇじぇ』という感じだ。入賞できなかったチームも悔しさをバネに来年は『倍返し』の気持ちで頑張って欲しい。人生は長い。どんなことも勝ち続けることは出来ない。負けないと次の勝ちもない」と流行語も交え子どもたちにエールを送る。
プログラム途中には滋賀発ダンス&ボーカルユニット「フリルフルール」、妹分の「フリフルシスターズ」のミニライブ、バルーンパフォーマー「つくもん」のバルーンアートショー、2010年度グランプリチーム「LAZU」によるダンス披露も行われた。
同大会ハイライトは1月25日15時30分から、びわ湖放送で放映される。大会結果はホームページで確認できる。【関連記事】 -
内部コミュニケーションの充実で完成度を高めるプロトタイピングツールInVision が$11.6Mを
3000万チャレンジプロジェクト
多くのWebデベロッパやデザイナーに人気のプロトタイピングツールInVisionが最近、FirstMark CapitalとTiger Globalによる1160万ドルのシリーズAラウンドを完了した。
ニューヨークで2011年にローンチした同社は、デザイナーたちが容易にプロトタイプを共有し、それらと対話し、フィードバックを得られることをミッションとする。ユーザはPhotoshopのファイルをWebに容易にアップロードでき、対話機能を加えてシミュレーションし、しかもそれらをすべて、ふつうのブラウザと一つのリンクでできる(パスワードによる保護もできる)。
2012年の2月にInVisionはFirstMarkによる150万ドルのシードラウンドを調達した。同社はその後、プロトタイプをめぐる会話の活性化に務め、いまではとても多くの人たちが会話に参加している。
ファウンダClark Valbergの説明によると、これまでプロジェクトの最終的なルック&フィールをめぐるデザイナーとコーダーのあいだのコミュニケーションは、内輪の人たちだけに限られていた。しかしInVisionを使うと、その会話が全社的になり、いろんな人からフィードバックが非同期で得られるようになった。
情報量が多くなりすぎてたいへんだろう、と思う方もおられるだろうが、でもデザインが完熟する前にプロダクトをローンチするリスクの方が大きい。しかしこれには異論もあり、複数のデザイン案が完成してからコーディングを開始すべきと主張するスタートアップもある。また、プロダクトの早期リリースが何よりも重要で、磨き上げはユーザからのフィードバックに依存すればよい、という説もある。
Valbergは以前本誌に対して、ユーザフィードバックによる段階的な磨き上げに反対ではないが、内部的な磨き上げを十分やらずに一般ユーザの手に渡ってしまうと、制御不能な深刻な問題が発生することもある、と述べた。
新たな資金は主に、さらなる顧客開拓に使われる。同社の顧客は、小さなスタートアップから大企業に至るまで、非常に幅広い。最近では有意義な(と思われる)パートナーシップの構築も進めており、マーケティング努力の充実や新機能の開発も今後のスケジュールに上(のぼ)っている。
InVisionのビデオはVimeo上のInVisionより。
(翻訳:iwatani)【関連記事】 -
SDNを取り巻く複雑怪奇なベンダー動向の全体像をつかもう
3000万チャレンジプロジェクト
前編「ネットワークだけではない、企業インフラがSDNに期待できること」では、2013年10月15~17日に開催された「ガートナーシンポジウム 2013」からガートナー ジャパン リサーチ部門 ITインフラストラクチャ&セキュリティ ネットワーク担当 リサーチ ディレクター 池田武史氏の講演を基に、SDN(Software Defined Networking)の概要と業界動向を記事にした。後編でも引き続き池田氏の講演を基にSDNの動向をお伝えする。
※前編:ネットワークだけではない、企業インフラがSDNに期待できること
→http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1311/21/news02.html
従来のネットワーク機器ベンダーの中には、ネットワーク機器をコモディティ化せずにハードウェアで差別化してたいベンダーも多い中、主要ネットワークベンダーはSDNにどう取り組んでいくのか。後編では、SDNに関わるベンダー動向とユーザー企業のSDNへの向き合い方にフォーカスを当てたい。
<<SDNに関連するベンダーを分類>>
一口にネットワークベンダーといっても、バックグラウンドはさまざまで、それぞれ事業内容や思惑は異なる。全体像をつかむために、ベンダーを幾つかに分類すると分かりやすい。
●ネットワーク機器ベンダー
ネットワーク機器ベンダーには、米Brocade Communications Systems(Brocade)、米Cisco Systems(Cisco)、米Juniper Networks(Juniper)、NECのように、ネットワーク機器に独自設計したネットワークプロセッサ(カスタムシリコン/カスタムチップ)を使用することで他社との差別化を図る老舗ベンダーと、米Arista Networks(Arista)や米Pica8のように、独自設計のネットワークプロセッサではなく、IntelやBroadcomといった商用チップを用いてネットワーク機器を提供する新興ベンダーの2タイプがある。
ネットワーク機器ベンダーの最大手はCiscoだろう。だがCiscoはSDNに対し微妙な立場を取る。「もともとネットワーク分野で成功を収めてきた同社は、OpenDaylightにも参加しSDNコントローラーのソースを公開する。だが、SDNにはいまひとつ積極的とは言えない」(池田氏、以下同)。実際Ciscoは、OpenFlowやOpenStackをサポートするなどオープンな仕様にも対応する一方、自社のコントローラー(「Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC)」)でネットワーク、また将来的にはサーバやストレージを含めたデータセンター全体をコントロールするという独自のSDN戦略も掲げている。
新興ベンダーではAristaの動きが活発だ。同社はネットワークスイッチがWindows Azureのデータセンターに採用されたことでも話題になった。「Aristaはネットワーク分野でCiscoの2番手に付くと明言している。今後、Brocade、米Hewlett-Packard(HP)、Juniperと戦っていくベンダーとして注目したい」
●サーバ機器ベンダー
SDNに取り組むサーバ機器ベンダーといえば、米Dell、米IBM、HPなどが挙げられる。
サーバ、ストレージ、運用監視ツールと、ITインフラ全般に関わるHPは、「ネットワーク分野ではCiscoに次いで2番目に付けているベンダーだ。OpenFlowには数年前から取り組み、対応製品を順次ラインアップし、これから数年かけてSDN基盤となる製品群を充実させていく方針だ」
IBMもSDNに積極的である。また、「Dellは、もともとコモディティ化したデバイスを売ることが得意なので、SDNがビジネスチャンスとなるかもしれない」
●ネットワーク仮想化ベンダー
ネットワーク仮想化ベンダーでは、米Big Switch、Midokura、米Nuage Networks、米Plexxi、米PLUMgridなどが挙げられる。中でもMidokuraは、ネットワーク仮想化に取り組む日本企業で、同社の製品は日本システムウエアなど国内のデータセンター事業者に導入されている。
●サーバ仮想化ベンダー
米Citrix Systems、米Microsoft、米VMwareなど、サーバ仮想化ベンダーもSDNに取り組んでいる。
この中で今、SDNを語る上で欠かせないベンダーがVMwareだ。自社製品での仮想化はVXLANベースを推しつつも、2012年に買収した米Niciraのネットワーク仮想化製品についても「VMware NSX」としてポートフォリオに取り込むという2面展開を図っている。
同社はスイッチやルータの仮想化だけを考えているわけではない。VMware NSXにFW(ファイアウォール)やADC(アプリケーションデリバリコントローラー)などの機能を搭載してきたところを見ると、ネットワーク機器をコモディティ化し、SDNでイニシアチブを取りたいと考えている。
「現時点ではVMware NSXにリッチな機能はないので、ハードウェア/アプライアンスベンダーを脅かすほどではない。また、仮想化ソフトウェアベンダーとして、彼らとのパートナー関係も大切であるから、今後も(表面上は)協業していくだろう。ただし、向こう数年ではハードウェア/アプライアンスベンダーと火花が散る争いになることも想定しているのではないか」
●ネットワーク周辺機器ベンダー
ネットワーク周辺機器ベンダーとは、FWやWAF(Webアプリケーションファイアウォール)、ADCなどを提供するベンダーを指す。米A10 Networks、米F5 Networks、米Palo Alto、米Radware、米Riverbed、などがそれに当たる。
彼らは、カスタムシリコンを使って製品に価値を生み出してきたベンダーだ。VMware NSXのような製品が台頭しても、「今すぐビジネスに影響が出るわけではないが、“SDx”の動きが加速する中で、次のビジネスを考えなければならないベンダーだ」。
<<SDNとの向き合い方>>
池田氏は「SDNは複雑怪奇な状況にあり、ベンダーの戦略や技術の成熟度も時々刻々と変わっていく。気を付けたいのは、SDNの動向を熱心に追うあまり、自社にとってSDNがどう役に立つのかという肝心な部分が抜け落ちてしまうことだ」と注意を促す。そうならないために、ユーザー企業は自分たちの立ち位置をハッキリさせることが大切だ。
●ネットワークのあるべき姿、SDNの適用領域を見定める
池田氏は「自社のネットワークのあるべき姿を把握することが大事だ」と述べる。
スマートデバイスやクラウドサービスの浸透は、企業ネットワークの在り方にも影響を及ぼしている。従来のように、物理的なクライアント端末やインフラの筺体だけを管理していても、ユーザーやサービスを追いかけることができない。ユーザーとサービスをつなぐという視点でネットワークやそのインフラを考える必要がある。
「ネットワークの役割を見直す時期にきている。やりたいことを実現するためにSDNがはまるケースもあれば、『NAC(Network Access Control)』とユーザー管理製品(Active Directoryなど)を組み合わせるなどの代替手段を取る判断もあり得る」
●ベンダーの覇権争いを見定める
ネットワーク分野の争いは、従来のスイッチ、ルータといったネットワーク機器に閉じたものから、さまざまな分野へと広がっている。DellやHPといったサーバ系、VMwareなどの仮想化系、Broadcomのような半導体系ベンダーが、ネットワーク機器ベンダーと共に覇権争いを繰り広げ始めている。
彼らの多くがOpenDaylightに参加しているベンダーだ。「彼らは、どういうモチベーションでOpenDaylightに参加し一体になって動いているのか。それは対Ciscoだ。Ciscoは長年、IPネットワークのリーダーとして君臨してきた。高くても使い続けるユーザーがたくさんいる。また、Ciscoはネットワークだけではなくサーバにも投資をしており、“Internet of Everything”といった未来のテクノロジーも視野に入れて活動している。だが、このSDxという大きな動きの中では若干逆風が吹いている。Ciscoがネットワーク分野で今後もリーダーで居続けるのか、あるいはゲームチェンジなのかは注目したい」
●設計や人材育成に課題も
その他、SDNに取り組みたいユーザー企業が考えることとしては、設計の複雑さや障害対応、人材育成などがあるという。これらの課題は、SDN技術や製品の成熟度に比例して解決しやすくなるだろう。
<<SDNは焦って飛び付かない方がいい>>
SDNに期待できることは柔軟性、迅速性、コストの最適化だ。ただし池田氏は、「SDNの成熟度はまだ低い。ユーザー企業は慌てて飛び付かない方が賢明だ」と注意を促す。上述した「SDNとの向き合い方」を考えながらじっくりと向き合いたい。また、「SDNを早期に導入する場合は、ベンダー任せではなく一緒にテクノロジーを育てていく覚悟が必要」とも付け加えた。
※「OpenFlow=SDN」ではない? ベンダー各社のSDN戦略
→http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1209/27/news05.html